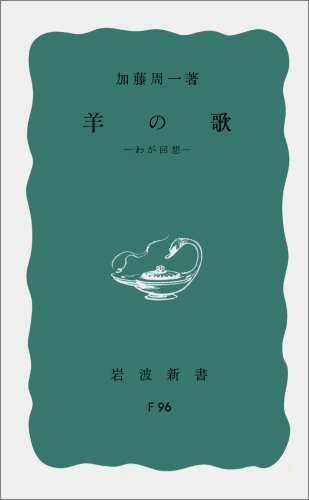虎というと山月記を思い出してしまうせいか、あまり落ち着かなくなっている。そのため虎の絵をかいていたが、猫にしようと思う。仲間だしいいだろう。
子供の時よく読んでいた本を古本屋で見つけたので、つい買ってきて、読んでいる。こんなものを読むから一層周囲になじめなくなったのだと思うが、やはりいい本だと思う。この本は続編もあるのだが、なぜか続編に関する記憶は全くない。教員免許を取ろうとしていた時、日本史の模擬授業をする際に、この本を教材に使った気がする。河上肇に関する部分を引用した気がするのに、今回読んだところには思い出す文面がなかったので、続編のほうだったかもしれない。河上肇の自叙伝があるというので、それもそのうちに読んでみたいよと思う。こういう本を読んで落ち着いているところを見ると、やはり私の感じ方考え方は私の読んだものによって慰められ、認められて形成されていったのだと感じる。それが今の生きにくさを生み出していると言われればその通りだと思うけど、それ以外の方向に自分が成長できたのか定かでない。
以下引用
しかしほんとうに信じていることと、信じていると信じようとしていることとは、ちがうのであり
その恢復期の間、生きていることは、それだけで、貴重なことのように思われ、傍から見れば取るにも足らぬ小さなことが、私には、世界中の何ものにも換え難いよろこびになった。一杯の熱い番茶、古い本の紙の匂い、階下の母と妹の話し声、聞き覚えのあるいくつかの旋律、冬の午後の澄んで明るい陽ざし、静かに流れてゆく時間の感覚・・・・・・そのとき、「死」とは、そのよろこびを私から奪うものに他ならなかった。私は自分の痩せた手肢をみつめ、それが焼けて跡かたもなくなるだろうということ、またその手肢を見つめている意識そのものが消えてなくなるだろうということを想像し、そうならざるをえないように出来上がっている世界の秩序そのものを、憎悪した。
私はいろいろな本が好きだったが、このように生きたいと思う人たちはちゃんとした職業についていた。加藤周一にしても医者だったし、セネカは皇帝の家庭教師だったし、文豪はちゃんと文豪だった。私は昔から何物にもなれていなかった。今も何物にもなれていない。
私は旦那と一緒にいるようになって、旦那さえ元気ならいいと思うようになったことはもちろんだが、今までただの箱としてとらえていた部屋が、一つ一つ役割を持った部分によって成り立っており、そこに置かれたマットや、それぞれの役割を持つ洗剤や虫殺しの薬などを生活だと大好きになったし、二人で話し合って買ったサボテンや、収納に一向に頓着しないでいる私に呆れつつ旦那が見繕って買ったきた食器を置く棚などをいとしく思うし、そんなちいさなことこそがわたしにとってよろこびであると感じるようになった。豪華な物品も、車も、豪邸も、旅行も、カメラもいらない。お互いが健康で一緒にいさえすればいい。
いかにしても死にたくはないし、旦那に苦労を掛けたくはない。この何物でもない自分が幸せに生きていくにはどうしたらいいのかと考え続けている。そのせいで憂鬱になっている。何物でもないままの自分では、追い詰められたときに人を殺して先に進むか、人を殺さずに自分が死ぬかしか選択肢がない。その時第三の道を開ける人間になるにはどうしたらいいのでしょうか。
最近旦那がなにか言うときに会社のことを引き合いに出してくると、心の中に不安が沸き上がって止まらなくなり、あまりのことに黙り込んでしまう。このような状況ではいけないと思う。職場のコロナ対応のあり様に対する反感と、この職場にとっての些事が私にとっては重大問題であるという、すれ違いのため、仕事について考えることがつらい。またその些事のために自分は罪の意識を感じていて、結局金儲けそのものが自分には適していないという風に今は思っている。おそらく利益を出すために仕事をするのであれば、私が気にしていることは些事であり、私のような一社員にとっても、お金をもっともっと稼ぎたいと思っているのであれば、このことは些事である。しかし私は自分の良心にかなう仕事をしたいと思っていて、最近はいっそ自分の良心の赴くままに会社以外の場所で働いたほうがいいだろうと、そうとしか考えられないではないかというようなことを思っている。これから不景気な時代が来るだろう。私は今度こそお金のためには働けないと思う。そしてこのタイミングで不景気になってくれるなら、お金のために働かなくていい。むしろ勉強する方向に戻れると思って、安心している。
職場で利益を生み出すための社員としてあまりにも不適切な自分自身の存在には何ということもできない。私の親戚には戦争が終わってから内地に帰ってきて、軍人として働いていた仕事を失ったものの、利益を出すこと自体が受け入れられず、どのような仕事にもつけなかった人がいた。その人は最後は塩を塩田で作る仕事を行っていたらしい。それ以外の仕事は一切続けられなかったそうだ。私が共感するその人物でさえ、「元軍人」だった。私は何物でもない。何物かになることをいつも避けてしまう。
本日図書館帰りにどこかを見て回りたいと思っていたところ、気になっていた洋食屋に人っ子一人入っていないので、入ってみることにしてカツカレーを頼んだ。驚くべきことにお店の人はマスクをしていなかった。控えめなクラシック音楽が流れる中で、ここは個人店なので、この人たちにとっては自分の家なのだということを思った。まるでコロナ以前の商店街に戻ってきたような気持になり、脳みそが呪いから解かれたような奇妙な気持ちになった。私はまずいところに来たと思い、すぐに帰ることを告げようと思ったが、なぜかそれができず、この店で食事をして帰るのだと強く思った。このときはじめて私は自分がコロナのない世界に戻りたいと思っている可能性もあると思った。私は基本的に戻りたいと思うことはない。起きたことは大体受け入れている代わりに、出会ってみなければ自分の考えも前もってはわからないというような類の人間だ。私は命を守りたいと思っているが、この店の人は違うものを守ろうとしているんだろうと思う。たぶんそうだ。本来様々なものを守りたいと思う人が存在し、互いに干渉しあわないのが東京のよいところだった。この特異な店に偶然入ってしまうことによって、変形した東京を見た。